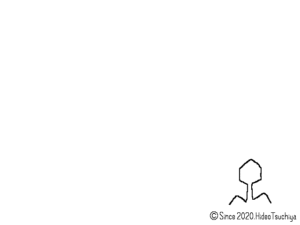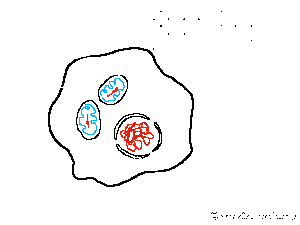【2】原形質流動とアクチンフィラメント
脊椎動物の骨格は、「リン酸カルシウム」でできている。
細胞の骨格は、「タンパク質」でできている。
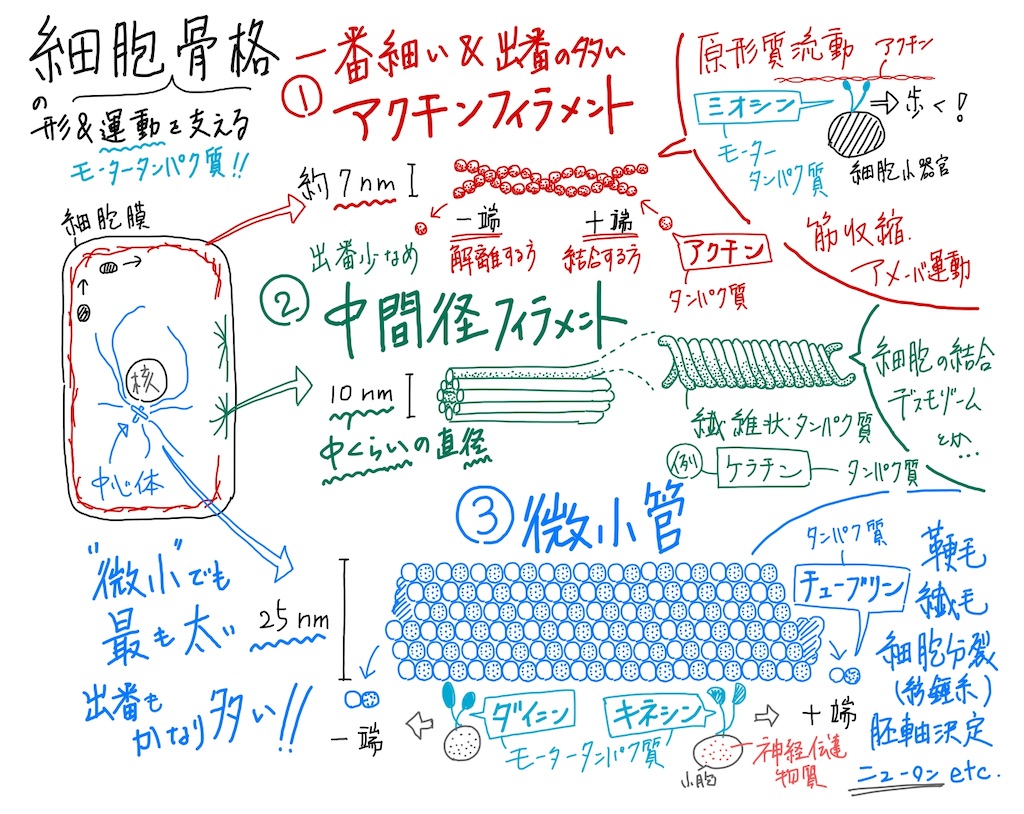
細胞骨格は大きく3種類。細い方から順番に・・・
- アクチンフィラメント・・・アクチン(タンパク質)
- 中間径フィラメント・・・ケラチンなどの繊維状タンパク質
- 微小管・・・チューブリン(タンパク質)
特に「1. アクチンフィラメント」と「3. 微小管」は、それぞれと関わりの深い“モータータンパク質”とセットで、『生物』の教科書では色々な単元にちょこちょこ顔を出してくる。
例えば“原形質流動“・・・。
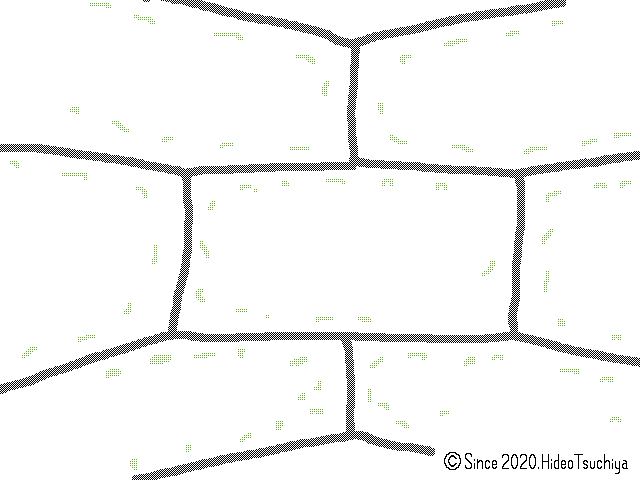
”モータータンパク質“の「ミオシン」が葉緑体などを”背負い“、細胞膜のすぐ内側ある「アクチンフィラメント」の上を”歩いて“いく。原形質流動の速さ(ミクロメータで計算できる!)を考えれば”走る”の方が適当かも。
とにかく「ミオシン」にすれば、一歩ごとにATPを消費する重労働。“原形質流動”が「生きた(元気な!)細胞でしか観察できない」ことや「適当に“流れている”わけではない」ことを納得してもらえるだろうか?
【補足】
- 原形質流動(細胞小器官が細胞内を“流れる”ように移動する現象)
- 細胞小器官(葉緑体とかミトコンドリアとか…)
- エネルギーの通貨“ATP”
- 1μm(マイクロメートル)= 1000nm(ナノメートル)
【参考資料】
- 吉里勝利(2018).『改訂 高等学校 生物基礎』.第一学習社
- 浅島 誠(2019).『改訂 生物基礎』.東京書籍
- 吉里勝利(2018).『スクエア最新図説生物neo』.第一学習社
- 浜島書店編集部(2018).『ニューステージ新生物図表』.浜島書店